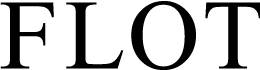ある日の、リアルタイム・フォロー。
(インナーブランディング_コラム)
「社員を主役に、企業が変わる。」を標榜するインナーブランディング・ソリューション「+ブランディング」。
今回は、実際のインナーブランディング・プロジェクトで筆者が最近取り組みはじめた「リアルタイム・フォロー」について触れてみたい。
まず一般的に「フォロー」と言えば、世の中のあらゆる商品・サービスの提供において、欠かすことのできないものに、「アフター・フォロー」が想起される。
それは、商品・サービス提供者が顧客に安心感を与えるうえで、また顧客と繋がりつづけていくうえで、あらかじめ商品・サービスに実装しているものと言っても過言ではないだろう。
このアフター・フォローの必要性や重要性は自明で、「あのブランドは、アフター・フォローがしっかりしているから」と、そうした信頼を前提に商品・サービスを選定する場面すらある。
贔屓にしているブランドがある場合を除き、デザイン性を含めて商品・サービスの内容や質、そして金額に大差がなければ、選定の最終判断基準はこのアフター・フォローに委ねられる可能性も大いにある。読者のみなさんも、そんな経験はないだろうか。
そうして商品・サービスそのものが良く、さらにアフター・フォローが行き届いていれば、顧客との信頼は確実に醸成されていく。
商品・サービスそのものを「形のブランディング」、アフター・フォローを「体験のブランディング」と捉えれば、アフター・フォローはブランディングに必要不可欠な一要素とも言える。
筆者がブランディング・プランナーとして関与するインナーブランディング・プロジェクトにおいても、アフター・フォローの重要性が語られることはしばしばある
「プロジェクトの提供のみで終わってしまっていないか」。
「プロジェクトで生まれたアウトプットを起点に、顧客に対してい新しいプロジェクト展開を提案できないか」。
「プロジェクト後に顧客企業で発生した新たな問題・課題に対して、何かしらの支援ができないか」。
筆者自身も、どんなタイミングで、どんなアフター・フォローをするのがベターなのかについて、しばしば壁にぶち当たる。
そしてこの通り、大抵アフター・フォローは、プロジェクト後に語られ始める。「アフター・フォロー」なのだから、「アフター(事後)」なのは仕方がないと言えば仕方がないのか……。
ここで「はて?」、と思った。
インナーブランディング・プロジェクトのように、準備期間〜アウトプットまでの工程も含めればほぼ1年間に渡って毎月、経営者や経営幹部と接点が持てる案件では、最低でも1カ月に1度というタイミングで「フォロー」ができるではないか。「アフター」なんて言っていたら、ほぼ1年後になってしまうではないか。
先に話した一般的なアフター・フォローと同様に「信頼の醸成」を目的とするのであれば、むしろプロジェクト実行期間中のフォローのほうが理にかなっているので、実行しない手はない。
インナーブランディング・プロジェクトを実行しながら、パラレルで顧客の悩み・問題・課題・疑問を丁寧に拾い、日々接点を持つパートナーだからこそ出せる答えで寄り添うのだ。
そして、こうしたタイミングで着実にフォローを行っていくことが、後々の「アフター・フォロー」の成果に確実につながっていくだろう。“日々のフォローなくして、アフター・フォローの成果なし”だ。
日々のフォローは、もちろん大変だろう。ちょっとばかり仕事が増えてしまうかもしれない。
それでも、顧客が目の前で壁にぶつかっている姿を見れば、壁をクリアする何かしらのフォローをするのが、パートナーとしての役目。
確実に言えることは、フォローを積み重ねた分だけ、信頼は着実に育まれる。醸成され顧客との強固な信頼のその先に、次の展開は自ずと立ち上がってくる。
筆者は、このフォローのスタイルを、「リアルタイム・フォロー」と名づけ、まず現在進行中で関与しているインナーブランディング・プロジェクトで実行してみようと考えた。
インナーブランディング・プロジェクトでは毎回の講義・ワークショップ後に、参加メンバーの社員さんたちに「プロジェクト参加レポート」を提出してもらっている。そこで気になったコメントを丁寧に拾い上げて、プロジェクトリーダーと経営者に対してフィードバック&フォローしていくという流れで、たとえばこんな感じになる。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
▶リアルタイム・フォローその1
[社員Aさんのコメント]
社員の認識や方向性は同じだろうと感じたものの、それに反して
日々の業務の連携がとれていなかったり、
むしろ社員が減っていたり等、団結してやらなければならないなかで、
良い空気を感じることができていないので、
インナーブランディングをする意味を再認識し活用していきたい。
↓
↓
↓
[フォロー例]
社員Aさんのコメントを拝見しました。
最後は、とても前向きな言葉で締めているのですが、
「日々の業務の連携がとれていなかったり」
「団結してやらなければならないなかで、良い空気を感じることができていない」という何か訴えたい社員Aさんの気持ちが現れていると感じました。
これは悪いことではなく、むしろ今回インナーブランディング・プロジェクトをやっているからこそ出てきた声なのではないかと感じました。
こうした一人の声をしっかりと拾い、改善に向けて動いていくことこそ、インナーブランディングを生かした社内の取り組みだと考えます。
つきましては、まず社員Aさんと、
「どう連携がとれていないのか?」
「どう連携をとれることが理想なのか?」
「どうしたら連携をとれるようになるのか?」
「どんな空気を感じているのか?」
「どうしたら良い空気を作ることができるのか?」などについて
いっしょに考え、さらにそれを部署内・全社に広げてみんなで話し合って改善していく方法を検討してみてはいかがでしょうか。
現在進行中のインナーブランディングで行っているように、チームごとに意見を出し合い、最終的に社内で意見をすり合わせ、解決策を導き出してみることをおすすめします。
▶リアルタイム・フォローその2
[社員Bさんのコメント]
自社の持つ強みをさらに強化し、弱い点を改善するための対策方法をさらに具体的にする必要があると感じた。
↓
↓
↓
[フォロー例]
今回のプロジェクトでは、「自分たちの強みを認識し、その強みが自分たちのお客様にとってメリットがあるのか、そしてその強みを通してお客様にしっかりと価値を提供できているか。さらにその強みを、どう自社らしさにつなげていくか」を重視し、「強み」にフォーカスしているため、「弱み」の導き出しは実行していません。
しかし今回「強み」を導き出すことで、社員Bさんはじめ社員さんたちは、もしかしたら自分たちの「弱み」も自ずと見えて、「弱みも、どうにかしないといけない」と思い始めたのかもしれません。
つきましては、今回見えてきた「弱み」については、たとえば各自から「弱み」の抽出を行い、その「弱み」をどのように克服していくかを社員全員で検討していくのも、インナーブランディングを生かした社内の取り組みになっていくと考えます。
ただし、克服する「弱み」は、最初は内部環境に起因するものにフォーカスしていくのが良いのではないかと思います。外部環境に起因する「弱み」は自分たちの力だけでは解決できない場合があり、大きな壁になってしまう可能性が高いです。
▶リアルタイム・フォローその3
[社員Cさんのコメント]
機能的価値・心理的価値を自社の強みとして最大化させていくために、業務改善を行いたい。
↓
↓
↓
[フォロー例]
こうしてインナーブランディング・プロジェクトで学んだことや導き出した内容を起点に、新たな取り組みを推進していこうとする考え・姿勢・行動はすばらしいと思いました。
今回、社員のみなさんで導き出した価値や強みに、どんな形で紐づいた業務改善を想定されているかぜひ知りたいです。
社員のみなさんを巻き込みながら業務改善について項目出しを行い、社員のみなさんとともにどのように実行していくかを考え行動していくことは、インナーブランディングを越えた社内の取り組みになっていくと考えます。
▶リアルタイム・フォローその4
[社員Dさんのコメント]
上位顧客は今まで以上に、下位顧客でも上位にできるように考えていけたらと思った。
↓
↓
↓
[フォロー例]
これは、営業戦略に関わることで、なかなか製造部門に所属する社員Dさんだけでは考えることはできないとは思いますが、こうしたことを製造部門の社員さんが考えていることに驚きました。
製造部門の社員さんがここまで考えているので、ぜひ社員のみなさんを巻き込みながら、下位顧客の売上を拡大する施策を考える場づくりをしていくことは、インナーブランディングを越えた社内の取り組みになっていくと考えます。
▶リアルタイム・フォローその5
[社員Eさんのコメント]
価値等を把握するだけでなく、スキルアップだったり、社員一人一人の協力が大事だと思うが、そういった空気だったり、流れを作ることができていないので、何とかしていきたいとは思う。
↓
↓
↓
[フォロー例]
社員Eさんは、以前にも「日々の業務で連携がとれていない」点について触れていました。ここでは、「スキルアップ」「社員一人一人の協力」について触れていますが、まず社員Eさんと話し合い、「どのようにしたらイメージしている空気や流れを作っていけるか」を社員Eさんに深堀りして考えていただき、それを改善・推進してく役割を社員Eさんに与えてみてはどうでしょうか(もちろんこの場合は、全社的なサポートが必要です)。
他の社員さんのレポートにも「改めてコミュニケーション・チームワーク強化がさらに必要だと感じた」と書かれているように、「社内の連携・協力」は、今後の社内改善のキーワードになると考えられます。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
筆者が直近で実践したリアルタイム・フォローを、ざっと5例ほど紹介してみた。
何ということはない。リアルタイムにフォローする内容は千差万別なうえに、そのフォローの仕方一つ取っても同じやり方はない。だからこそ、フォローの内容そのものというようよりは、リアルタイムにフォローしていく意識・姿勢・行動そのものを参考にしてほしい。
漫然とプロジェクト(案件)を進めるだけでなく、プロジェクトを進める中で生まれた疑問や悩み、問題・課題に、その場・その瞬間にリアルタイムにフォローを行っていく。これが、リアルタイム・フォローの真骨頂だ。
“フォロー力”の向上は、提案分野に関する専門知識の向上とフォローの場数に比例する。要は慣れれば、フォローの質やレベルは自ずと向上していく。だからこそ、テクニックに走ることなく、リアルタイム性を重視したい。
ちなみに、もう読者の誰もが気づいているだろうが、アフター・フォローとリアルタイム・フォローに優劣はない。要所要所で適切に、丁寧にフォローを行う体制とアクションが重要なのだ。
最後に、今回のリアルタイム・フォローで筆者が特に心がけたのは、「ブランディング・プランナーとしてフォローする側が、すべてに答えを出してしまわない」こと。プロジェクトリーダーや経営者が、社員を巻き込みながら、社員のみなさんとともに自立して答えを導き出していく力を育んでいけるように、プロジェクトリーダーや経営者、社員のみなさんに答えを委ねる柔軟さを意識してみた。これは、テクニックか……。
「+ブランディング」では、今後もインナーブランディング・ソリューションを中心に、企業において社員と経営者が一つになり、めざす未来へ向かうためのお手伝いをしていきたい。
では、また。ある日に…。
Branding planner OKADA Kenya
TAG(注目キーワード)
その他の記事を読む
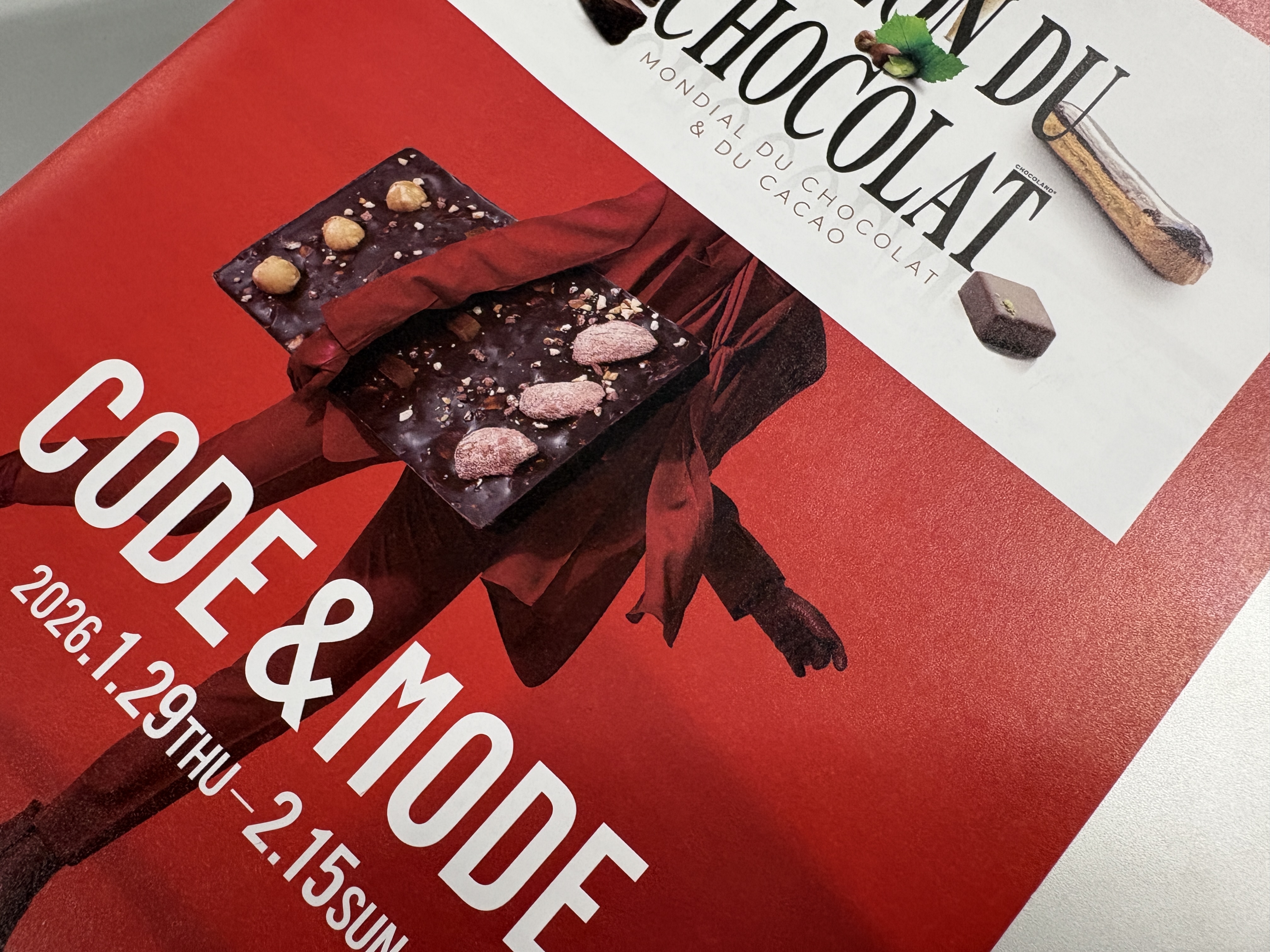
NEW
2026.02.03
ブランド価値逆転の主戦場、
バレンタイン。毎年この時期になると、いそいそとある百貨店の催事売り場に向かってしまいます。
それは、チョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ」。
NEW
2026.01.30
2026年、冬。
努力の蕾が花開くその時まで。2026年の幕開けから、早くも三週間が過ぎ去ろうとしています。
1月。それは受験生にとって、一年で最も冷たく、そして最も熱い季節の到来です。
NEW
2026.01.15
ユーザーが迷わないサイト設計

2025.12.26
わたしは、形から入るタイプです。
みなさんは、
「形から入るタイプ」ですか?
それとも「中身や本質から入るタイプ」ですか?
わたしは、完全に「形から入るタイプ」です。
「形から入るタイプ」と聞くと、
物事を始める際に、
その本質や内容よりも、見た目や体裁を先に整えることで、
モチベーションややる気を高めて行動につなげる人!
というイメージがありませんか?
わたしの場合、その傾向は、
ものを選ぶとき(購入を決めるとき)の判断基準にも表れています。
① 形(見た目・自分のライフスタイルにマッチするか)
② 中身(性能・品質)
③ 値段
(+αで背景やストーリーなど)
①②③すべてに納得できたときだけ、購入を決めます。
中身が良くても、見た目が好みでなければ選びません。
見た目が良くても、中身が伴っていなければ選びません。
「他に良さそうなのがないから、これでいっか!」
という妥協も、できるだけしたくありません。
ECサイトやホームページ、チラシなどでも、
これまで特に関心のなかった商品なのに、
「デザインがいい」というきっかけから、
中身を知りたくなることがあります。
スーパーの野菜売り場で、
農家さんの写真や言葉が丁寧に添えられているだけで、
少し高くても「ちゃんと選びたい」と感じることもあります。
この感覚は、たぶんこれからも変わらないと思います。
「形から入るタイプ」というと、
「形より中身でしょ!」という声があると思います。
しかし、形が整うことで、やっと中身に向き合えるなら、
わたしはそれもひとつの方法だと思っています。
理想やブランディングも同じで、
どれだけ強い想いや価値があっても、
伝わる「形」がなければ、その「中身」まで届きません。
このことから、わたしは、
形は、中身への入り口だと思っています。
そう考えると、
形から入るタイプでも、悪くないですよね??
2025.12.05
アニメやゲームみたいに
「刺さる」大学の広報づくりを!「このキャラに救われた」「この作品に人生を変えられた」―自分の好きなアニメ・ゲームをSNSで検索してみると、そんな言葉で感想を綴っている人たちを見かけることがあります。