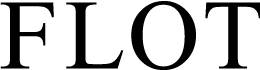シニアを一括りにする勿れ

シニアマーケティングというマーケティングの専門分野が存在します。
しかもそれはこれから、いえ、すでに急成長している分野なのです。
超高齢化社会への突入が危惧されて久しいわけですが、それを聞くと何となく「残念な」気持ちになります。昔からの「シニア像」、例えば、歳を取ると身体のあちこちが弱くなり、思考面でも新しい事を受け入れられなくなり、社会からリタイアし静かに死に近づくというイメージが、「残念な」印象を持たせているのかもしれません。
しかも従来のシニアを一括りにしたマーケットで売るものといえば、「健康食品」「育毛剤」や「白髪染め」「シニアグラス」等々、身体的ネガティブを補うものばかり。一方、親の介護が終わりシニアに片足を入れた私や同世代の友人が、プライベートな時間やお金を何に使っているかといえば、トレッキングやマラソン、Netflix、オンラインゲームや推し活、ネイル、ハーブ菜園。実に多岐に渡りその情報源はSNSやWEBサイトが中心です。
そうです。既にデジタル化を受け入れている新シニア世代(デジタルシニア)を、一括りで「シニア」とマーケティングしてはいけないのです。
シニア層を4つのゾーンで分類する考え方があるようです。
1/アクティブシニア(就労健常人口)
2/ディフェンシブシニア(非就労健常人口)
3/ギャップシニア(介護予備群人口)
4/ケアシニア(要介護等認定人口)
アクティブシニアとケアシニアは、これまでも良く耳にしましたが、その間にあるディフェンシブシニアとギャップシニアは余り認識されていませんでした。働く元気な人が突然要介護になるのではなく1から4まで徐々に変化していくというものです。しかも実はこのディフェンシブシニアとギャップシニアの人口がシニア全体の6割超を占めているのも特徴的です。
さらに、詳細な消費者像を設定する「ペルソナ」では、シニアを「時間の使い方」で分類する事ができ、上記の4つのゾーンに価値観(時間の使い方)を加えるととても興味深いものになります。
例えば最近注目の「モラトリアムおじさん」というペルソナがあります。「企業戦士」のように会社に人生をささげてやっと定年を迎え…身体が元気ではあるものの「果敢に行動するアクティブシニア」のイメージとは程遠く、「しばらくぼんやりしたい」「時間ができても何をしていいかわからない」と考えるシニア層です。
確かに当社でも定年退職された方々を思い出すと、現役の頃から趣味を愉しんでいる方よりも仕事オンリーの社会人生活を終えて引退された「おじさん」の方が多いように思います。この「モラトリアムおじさん」が、これからの攻略マーケットになる、という説が注目されています。
数年前、団塊世代が60代に差し掛かる時に「アクティブシニア」という言葉が生まれ100兆円とも言われる市場で消費が拡大すると見込んだのに、思ったほど成功していないと言われています。「アクティブシニア」はシニアの一部でしかないのに、市場のすべてを「アクティブシニア」が消費すると誤算したのが要因との事。
最大人口の団塊世代が70代半ば、団塊ジュニアも50代に差し掛かり、その間にはバブル期にお金の使い方を覚えた60代がいます。この大きなマーケットの人たちに、まだまだ稼いで元気に消費してもらう事が、人口が少ない若年層の助けになるともいえるのですね。
私たちは、今こそ改めて「シニアマーケティング」に着目してみたいと思います。
次回はシニアをターゲットとした時の、「表現のコツ」について。
※シニアとは/WHO(世界保険機構)では65歳以上と定めています。
(65歳から74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者)
※参考/株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室
株式会社ビデオリサーチ「新シニア市場攻略のカギはモラトリアムおじさんだ!」
Brand Control Adviser K.IGARASHI
TAG(注目キーワード)
その他の記事を読む

NEW
2025.07.11
ウェブサイトって、
作ったら終わりじゃないんです!
NEW
2025.07.03
「ファンになる」瞬間から学んだ
発信し続けることの大切さ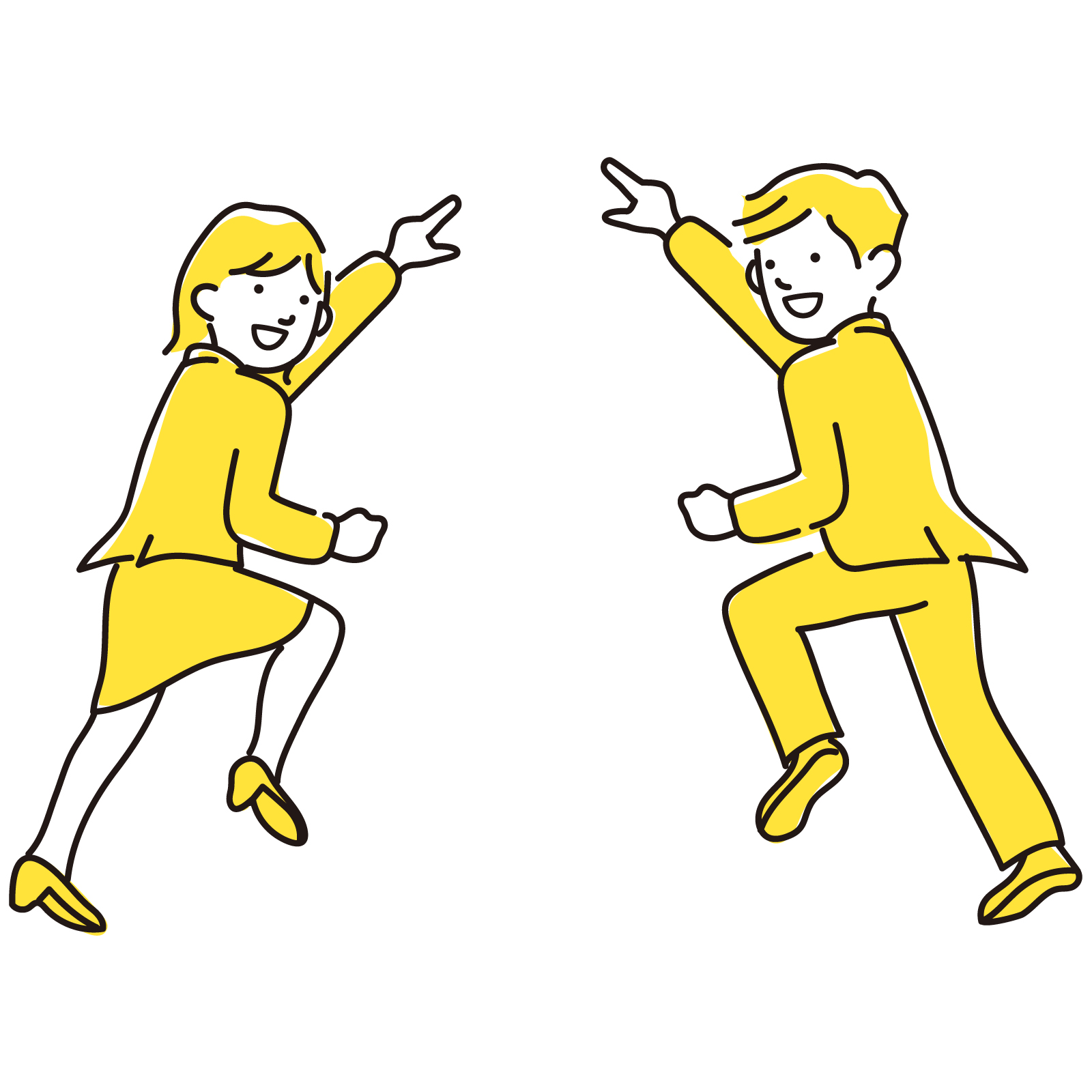
NEW
2025.07.02
保護者にも伝えたいことが
たくさんある!
一緒に体験するオープンスクール!初めまして!EMTメンバーのかなざわです。

2025.06.17
「見つけてもらう」ための
マーケティング?
私自身、何かを深く知りたいと思うと、とことん調べて、関連する情報を次々と読み漁ってしまうタイプなんです。
きっと、皆さんも経験があるのではないでしょうか?
その「調べる」という行動の中にこそ、今の時代に合ったお客様との出会いのヒントが隠されていると感じています。
皆さんは「マーケティング」と聞いて、どんなことを思い浮かべますか?
2025.06.10
進路選びの第一歩に。
「オープンキャンパス」の歩き方進路について考えはじめた高校生や、そのご家族にとって、
「オープンキャンパス」は将来の大きな一歩となる大切なイベントです。